平日のある朝、社員達が「おはようございます」と次々に出社する。「ちょっといいですか?」と仕事の相談を持ち掛ける人もいれば、雑談する人やいそいそと作業に取り掛かる人もいる。
よくある光景だが、彼らが出社するのは “オフィスビル”ではない。インターネット上にある仮想の“バーチャルオフィス”。…と聞いてもにわかには信じられないかもしれませんが、これは、創業10年のシステム開発会社、
株式会社ソニックガーデンの日常風景です。約40人いる社員のうち半数は地方在住。中には世界各国を旅しながら働く社員さえいます。
彼らが持たないのはオフィスだけではありません。上司もノルマもなし。働く時間や場所、休暇や経費も、誰にも管理されることなく個人の裁量に委ねられています。しかも、収益、社員数ともに右肩上がりで成長を続け、2018年には“働きがいのある会社ランキング”第5位を受賞。働きやすさと働きがいを両立する仕組みやビジネスモデルについて、代表取締役社長 倉貫義人様にインタビューしました。
INDEX
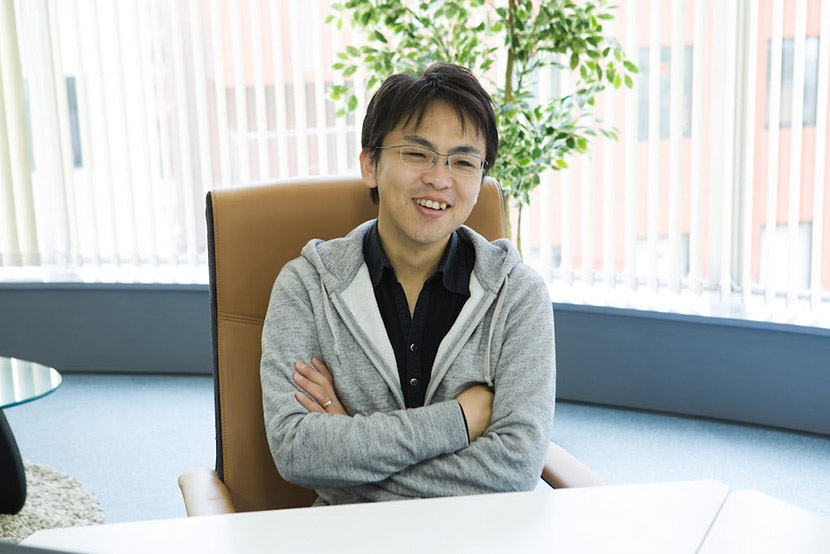
今回お話を伺った代表取締役社長 倉貫義人様
社員を管理しても成果は上がらない
こういうユニークな働き方を始められた背景から教えていただけますか。
はい。まず前提として、プログラマーの仕事って細かく指示命令されたからといって良いものができるわけじゃないんです。自由に働けて自分の裁量で動けた方が、生産性が上がって高品質なものが出せる、というのも僕自身がプログラマーだったのでよく分かるんです。
それで、なるべく管理しないで品質や生産性を上げる方向にやり方を切り替えていった、と。
すると成果も出てきたので、この方向で進める流れになりました。
2016年にはオフィスを撤廃して、全員がテレワークになったそうですね。
もともと地方在住の人から応募があったので、その人を採用する為に在宅勤務制度を作って、それを続けていたら地方の人がだんだん増えていったので、いっそオフィスもなくして、みんな自由に働くようにしたらいいじゃないか、と。
初めに倉貫社長がおっしゃった、“生産性が上がる”とは具体的にどういう事でしょう?
たとえばシステム開発の業界で言えば、長いスパンで見た時に、システムの“保守性”が高い状態=生産性が上がった、ということだと思っています。
“保守性”とは?
保守性とは、システムの修正・改修のしやすさのことです。
例えば、システムに不具合が出て修正が必要になった時、保守性が低いと、つまりぐちゃぐちゃに作ってあると修正に時間が掛かってしまいます。でも、保守性が高く綺麗に作ってあればすぐに直せます。
保守性によって品質の差がすごく出るんです。
かといって、社員が書いたコードの一字一句を指示することもチェックすることも不可能。
ならば細かく指示命令するより、最初から本人に任せてしまった方が良い、と判断しました。
プログラマーこそ、社内外のコミュニケーションが重要
マーケティングの世界では商品開発のヒット力や革新性などはコミュニケーションから生まれる事が多いと実感しているのですが、プログラミングの世界ですとその辺りはどうですか?
プログラミングもコミュニケーションをしないと良いものは作れません。プログラムと聞くとコンピューターに向かって作業するだけに思われがちですが、僕らの会社はそうではありません。
直接お客様とプログラマーがお話しして、お客様の困りごとをプログラマーが解決する。だから、ただ手を動かす仕事ではなくて問題解決する仕事なんです。コンサルタントがプレゼン資料を作るように、僕らはプログラムを書く、というわけです。
確かに、問題解決するにはコミュニケーションは不可欠ですね。
お客様だけでなく、社内のコミュニケーションもです。
それぞれ得意/不得意分野があるし、色々なアイデアを持っているメンバーと議論や相談をして、解決したり良いアイデアが出ることって多い。だから、コミュニケーションは欠かせません。
社内のコミュニケーションはチャットですか?
チャットもありますが、チャットって相手が今いるかどうか分からないから、声を掛けにくいんです。
1対1のチャットだと健全さが保ちにくいので、チャットは大勢が見ているところすべきなんです。
でも、大勢の前で誰かに声を掛けてスルーされるとすごく恥ずかしい。スルーの理由が無視なのか離席中なのかも分かりません。
オフィスなら、いる/いないがすぐ分かるから声を掛けやすいですよね。いれば掛けるし、いなければ掛けない。
チャットでも、いる/いないがすぐ分かればいいですが難しそうですね…。
そんな事ありません。オフィスでできる事をオンライン上でもできないか?ということで生まれたのがこの“バーチャルオフィス”です。仮想的なオフィスをインターネット上に造って、会話したり仕事してるんです。
見てみましょうか、ほら。

同社が開発した、リモートワーク支援ツール“Remotty(リモティ)”(https://www.remotty.net/)のデモ画面
在宅勤務でもコミュニケーションが重要なので、それをしやすくする仕組みのひとつです。
ログインすることを“論理出社”と呼んでいて「おはようございます」って言ってログインしてきます。そこで、
話したい人がいれば、例えば、神奈川-兵庫間でも「ちょっといいですか?」といって普通に会話を始める、と。
皆さん、日中に働くんですね。プログラマーの方はてっきり夜型かと思っていました。
大きな偏見ですね。夜型でも何型でもコミュニケーションしないと成果が出せない、とみんな分かってるので昼間に働いているのです。
こういう職種だと、ネットコミュニケーションのリテラシーも高かったりしますか?
そうですね。
以前、友人とFacebook上のやり取りでカチンとなった経験があって。対面ではそんな事ないのですが、なぜかネット上だと言葉がきつく感じたりする事はありませんか?
う~ん、ネットだときつくなる人は…慣れてないのかも?テキストで会話してても配慮して話せば変わらないと思います。メールだとカチンとくる内容は書かないはずなので、チャットだからダメという事はないと思います。
バーチャルだってFace to Faceは実現できる
バーチャルでもコミュニケーションを大事に仕事していらっしゃいますが、リアルに対面するのと比べて差は感じたり、対面で話したくなる時はありませんか?
これも勘違いされてる気がしますが、Face to Faceで話した方が良いと思います。
チャットがマストではないし、Face to Faceで話したいと会話したければこうすればいいんです。ほら。

TV会議ツール“zoom”を使ったコミュニケーションの様子
(普段はテレワークだが、時々リアルなオフィスに出社する事もあるという社員に対して質問)自由が丘のオフィスにあるワーキングスペースに出社して仕事をされる事もあるとお聞きしましたが、実際にオフィスに来るのはどういう時ですか?
(モニター越しの社員の方)自由が丘のWi-Fiルータのアップデートやちょっと寂しい時とか(笑)
仮想オフィス上で社員の顔も見ているので、一体感というか皆で仕事できてる感じはあるんですけど。
やっぱり寂しいですよね?私も独立して最初に感じたのは、人がいない寂しさや何か思いついても声を掛ける相手がいない事だったんです。
(倉貫社長)彼の場合は、独身で一人暮らしだからというのもあると思います。家族と同居している人から「寂しい」とは聞いたことないです。声を掛ける云々ということなら、雑談から真面目な相談までバーチャルオフィスでできますし。
TV会議は2人以上でもできるんですか?
はい。何人でも社員全員でもできます。基本的にみんな各自チャットで仕事してるので。声かけてみましょうか?お~い。ね、集まってくるでしょう?(画面を見ながら)

画像は、全員が各自のPCから参加する「オンライン飲み会」の様子。出入り自由、満足して帰りたくなったらログオフすればOK。
社員の半数が地方在住で、自宅で作業する人が多いです。物理的に会ったことがない社員もいますよ。
彼は兵庫県在住ですが昨日まで海外を渡り歩いていて。お~い。(と画面に呼びかける。)
(社員の方)はーい。
昨日まで海外にいらっしゃったそうですが、お話を伺ってもよろしいですか?
はい。一ヶ月半、バリやジャカルタに行っていて、平日は現地のホテルやコワーキングスペースからログイン出社して普通に仕事していました。
わぁ…、なんだかカッコイイですね。ありがとうございます。
(社長)モニター越しの背景にやけに外国人が映り込むなと思って、聞けば外国だった、という。
オーストラリアでキャンプしながら仕事をしている社員もいて、いつも背景がテントなんです(笑)。
ちなみに、自宅の部屋が映り込むとなんだか雰囲気にそぐわない、という場合にはこんなポスターを貼ることもあります。

ワークプレイス風のポスターを壁に貼る、という意外にもアナログな手法(!)
ここまで見てどうです?遠くにいる感じ、しなくないですか?
びっくりしました。物理的に会うのとまったく変わらないです。何かが失われるわけでもないし、むしろリアルに対面するよりも無駄に気を遣わなくていいから、楽なくらいかもしれません。
仕事部屋や合宿など、物理的な“場”も提供
「家だと仕事モードになれないから在宅勤務は苦手」という声もよく聞きますが、御社ではどうですか?
もちろん家で仕事しづらいという声もあったので、「じゃあ、借りればいいんじゃない?」という事で、仕事部屋を会社として契約しました。今、全国に4ヶ所あって、いつ来ても来なくてもいい、集まる為の場所じゃなくて作業するためのスペースです。
課題やこれから考えていることは何かありますか?
働き方に関してだけなら問題ないですね。
新しい取り組みは一年くらい前から、自由参加の社員旅行みたいなものを始めました。
ハッカソン(※)というプログラムを作ったりする合宿で、基本的に遊びのようなものです。
ずっと家で仕事をしていると気分転換したくなる時もあるでしょうから。
家族の同行もOKで、その分の旅費を半額出す“合宿の友”という制度もあります。
※ハッカソン…プログラマー達が集まり与えられたテーマに対するシステムやサービスを数時間~数日の短期間で開発し、その成果をチームごとに競うイベント。
経営ビジョンを共有するような全社会議もないんですか?
ありません。全員が集まるのは、年一回、社員とその家族を招待して泊りがけで遊んだりする
“家族旅行”の時だけです。

選考期間1年半+勤務地不問で、全国の優秀な人材だけが集結
採用にパワーを掛けているそうですが、詳しく教えていただけますか。
中途採用の場合、採用までに1年~1年半かけます。その間ずっとコミュニケーションを取って、合宿に参加してもらったり、仕事をお試しでしてもらったり、ハッカソンで遊んだり、飲み会ももあったり。
こういう事を重ねて、お互い「いいね!」となったら採用になります。
入社までかなり時間を掛けるんですね。
普通の会社だと転職は基本的にギャンブル要素が強いです。あたりはずれがやってみて初めて分かる。
はずれでも我慢するしかない。そうならない為には入社前に試した方がいいよね、って話で。
面接2回だけして採用するのは、例えるならデート2回で結婚するみたいなものでしょう?
怖くないのかな、って逆に思います。僕らはデートも同棲もして結婚に至る、と。
はずれの場合、会社側も社員側もお互い不幸ですよね。
時間を掛けただけ信頼関係も築けます。入社後に関係構築するより、入社前の方がリスクが低いです。
僕らの会社は働く場所や時間、経費も自由。中間管理職、つまり指示命令する人もいません。
決裁も評価も、売り上げ目標や個人ノルマもありません。
えっ…、経費の使い道も自由ですか?
はい。会社のクレジットカードの暗証番号を共有してますし、使い道もチェックしません。
評価がないという事は、給与はどうしてるんですか?
給与は職種ごとにほぼ一律で、賞与は山分けです。
進捗管理も本人がします。納品がありませんから、担当になったプログラマーがずっとお客様とお付き合いしていく、“顧問弁護士”のようなイメージですね。
チェックなしでトラブルに発展する心配はありませんか
ほとんどありません。なぜかというと、お客様には初月無料で弊社を試してもらってから契約してもらうのです。
試してもらった結果、契約に至らないとしたら仕方ないです。
では営業活動はどうしてるんですか?
全てWEB問合せのみで営業社員はいません。今は有難いことにお客様に待っていただいてる状態です。
顧客数や毎月の売り上げ推移、商況もほぼ見ていません。一度契約してお客様が満足していただける限り続くストックビジネスで、波があるわけではないので、お客様に満足してもらえる様にだけ頑張ることが大事なんです。
ちなみに、総務的なルーチンワークは全てシステム化して自分達でやるので事務社員もいません。
会計関係だけは税理士と契約していて、オンラインでやり取りしています。
魅力的な働き方ですから、入社希望者も多いんじゃないですか?
そうですね。元々は、5人で起業して採用活動をする時、勤務地を東京だけに固定すると応募が集まらないと思ったので、
勤務地不問で応募を掛けたら全国から応募が来たんです。
全国の優秀な人だけ集めた上にパワーを掛けてマッチングまでして。ここまでやると辞める人も少なそうですね。
創業10年で今まで退職者は1人かな?その辞めた人も、フリーランスになって僕らの仕事を今も続けてるので、ほぼ辞めた人がいない状態ですね。
退職者ゼロ?!すごいですね。
入社後は上司も管理者もいない、全く管理しない状態なので管理コストが圧倒的に低いんです。
だけど、僕らはその分を採用コストに掛ける、と。
よく分からない人を採用して「悪いコトしないか?!」って疑いながら管理するより、
採用前にコストを掛けて安心した人だけ採って管理しないか、の違いなのです。
合理性のある判断をしているわけです。
だったら、入社前に見た方がお互いハッピーですよね。
どこの会社もそうすればいいのになぁ、って思います。このやり方は性善説とか言われますが、
僕は世の中悪い奴しかいないと思ってるので(笑)、入社前にしっかり見極めないと怖いな、と。
全部の会社がそうなると、悪い人は就職できなくなりますね(笑)。
そうなると、悪い人は仕事できない。「ちゃんとしなきゃ」って心を改めて世の中良くなるんじゃないでしょうか(笑)。
“納品のない受託開発”で、社員もお客様もWin-Win
ははは。人間を善にする仕組み、みたいな。
僕らのビジネスモデルも、先ほどの話とも繋がりますが「良い人をつくる仕組み」だなと思っていて。
普通のシステム開発って、良いものを作ろうと思っても納品期限が迫ると「手を抜かないと間に合わない!」って悪魔のささやきに負けて、保守性の低いものが出来てしまうことがあります。
すると将来的にお客様は苦労しますが、会社側は納品すれば終わる仕組みだから将来の保守性まで関心がいかないんです。プログラマー本人も手抜きしたいわけじゃなくても納品しなきゃいけないので、しぶしぶ悪に手を染めるときもある、と。
でも御社の納品がない仕組みなら、そうはなりませんよね。
僕らは納品という観念がないので、ずっとシステムの面倒を見なきゃいけません。
つまり、保守性の悪いものを作って苦労するのはプログラマー本人なので、良いものを作ろうとします。
納品がないという事は、どういう料金体系になるんですか?
月額定額制の顧問スタイルです。
普通のシステム会社は、見積もりを作ってお金を貰う形なので、ついお金がかかる提案をしてしまうことも起きてしまいます。
僕らは定額なので、お客様が無駄なものを欲しがっても「やめましょう。その分のお金で他の事しましょうよ」って
提案できます。お客さんは無駄なお金を使わなくて済むから、すごく喜んでくれます。
これは定額制だからできること。だから、ビジネスモデルで人格って作られるのかな、と思うんです。
未来は意外とシンプル?
非常に未来的ですよね。これから技術発展してVRが凄いことになると言われていますが、そういうSF的なレベルで考えていることはありますか?
僕たちの働き方自体が、世間一般の人からすると十分SFの世界かもしれないですよね。
それに、夢見がちに“未来”を語ると、ドラえもん的なアニメの世界に出てくるようなものを想像しがちですけど、現実的な未来はもっとシンプルなものになるんだろうな、と。
あまりとっぴな事態は起こらないだろう、と。
例えば、スマホって昔の人から見ると“未来”だと思うんですけど、当時の人が、翻訳機能もカメラも付いて動画も見られて世界に配信できる物を想像したら、こんなの(スマホを指す)じゃなくてもっとゴテゴテした大きな物を想像するはずです。
でも、実際に完成したのは薄くてシンプルなスマホ。
本質を捉えていくと、未来というのはシンプルで、今の延長線上で実現するんだと思います。
御社の働き方でいうと今のままで充分満足ですね。
今の時点であれば充分ですね。
セキュリティが心配?原因は知識不足かも
テレワークのセキュリティ性を心配する企業も多いですが、その辺りはどうですか?
むしろ、セキュリティの何が心配でしょう?
えーと…基本的には個人情報の取り扱いとかでしょうか。「何らかの悪い事に使われそうな気がする」的な。
“アナログは安全、デジタルは怖い”は知識不足が原因だと思います。
明治時代に「写真を撮られると魂が取られる」と言っていたのと同じ感じじゃないでしょうか。
分からないから怖いし、知識がないから危ないのです。セキュリティに関してもきちんと知識を得て対策してしれば、むやみに怖いことなんてないですよ。
今後は女性や高齢者、外国人の活躍がカギになっていくと言われていますが、倉貫社長のお考えを伺えますか?
当社の場合は、単純に能力の問題で、応募があって良い人なら採用する方針です。
様々な方を敢えて採用しようとか、逆に排除しようとも思いません。
“多様性”ってよく聞きますが、多様になった状態を受け容れるのは経営者としてすべきですが、多様にするために敢えて受け容れるのは本末転倒ではないでしょうか。
本日は大変勉強になりました。貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今回協力して下さった企業様
株式会社ソニックガーデン
- 設立
- 2011年7月1日
- 創業
- 2009年5月1日
- 本社所在地
- 東京都世田谷区奥沢7-5-13
- 事業内容
- クラウドで動くウェブアプリケーションの受託開発、オリジナルブランドのソフトウェアの提供等
- 従業員数
- 約40名(2019年1月時点)
- Webサイト
- https://www.sonicgarden.jp/





